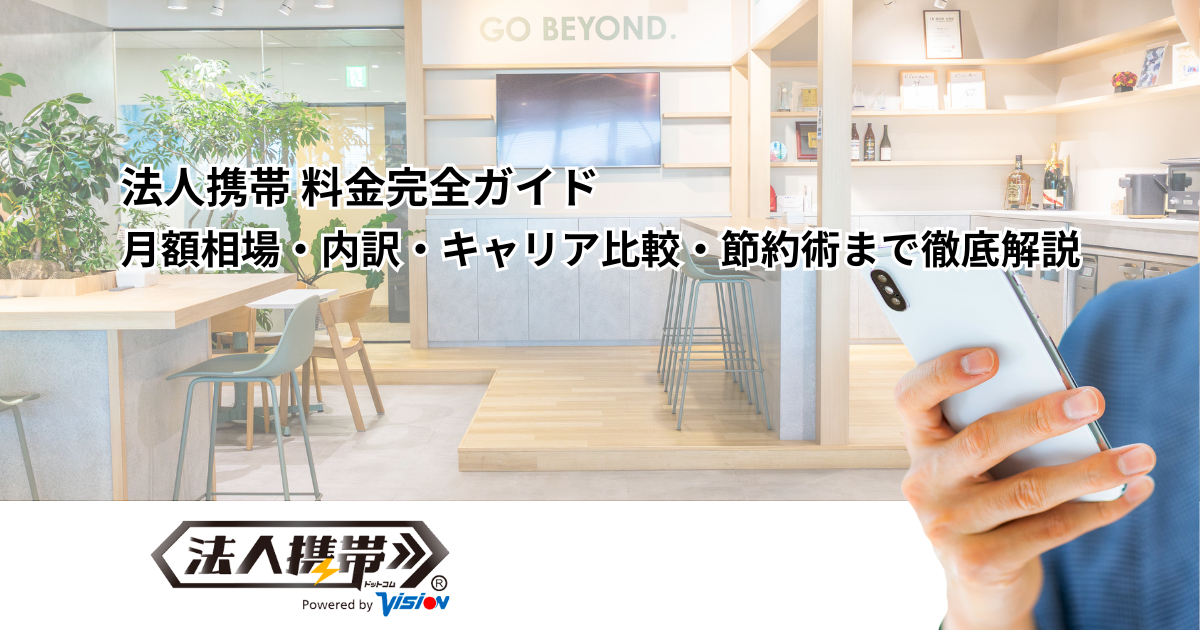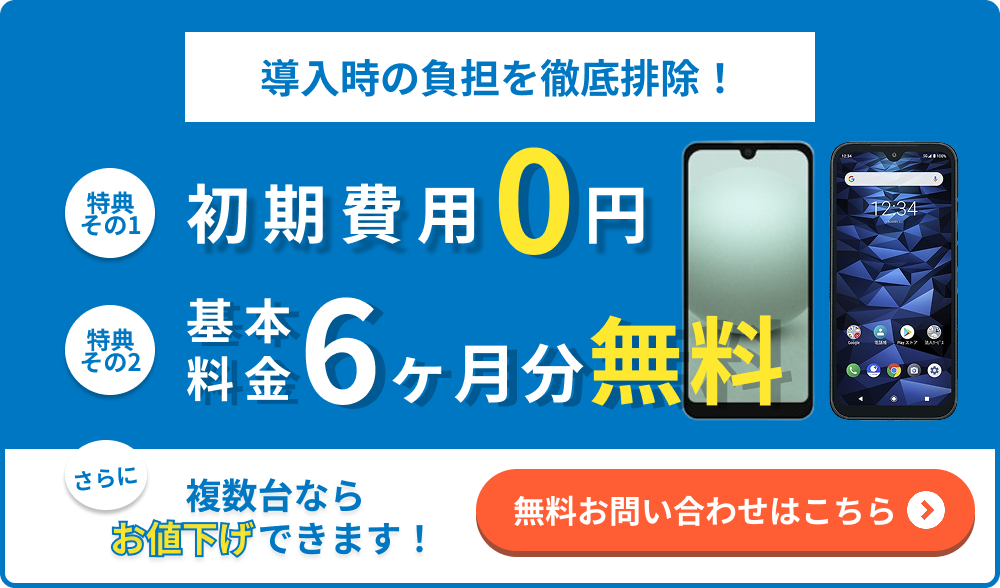目次
法人携帯の料金について検討する際、大まかな月額相場やプランの比較、さらに節約のための方法などを理解しておくことはとても重要です。
料金構成が複雑になりがちな法人携帯でも、ポイントを押さえておけば導入から運用までスムーズに進められます。
本記事では、初期費用から月額料金までの内訳に加え、キャリア別プラン比較や業種別におすすめの選び方など、実践的な情報を幅広くまとめました。
企業が必要とする通信環境を見極めると同時に、コストを最適化するための具体的な方法も紹介します。
初心者の方でもわかりやすいように、専門用語をなるべく避けながら、契約前・契約後に気をつけたいポイントを丁寧に解説しています。
法人携帯を導入するかどうか迷っている方や、すでに利用しているがコストが気になるという方も、ぜひ参考にしてみてください。
法人携帯の料金体系の仕組み
法人携帯は個人向けとは異なり、企業ニーズに合わせた独自の割引やプラン構成が用意されている点が大きな特徴です。
一般的に法人携帯では、一定の回線数をまとめて契約することでボリュームディスカウントが適用されるケースが多く見られます。
例えば大手キャリア各社では、複数回線の契約で基本料金が下がったり、データ通信量が共有できるプランが提供されていることがあります。
また、法人契約の際にはLinuxサーバとの連携や外部システムへの接続など、個人利用とは異なる要望が出る場合もあります。そのため、キャリア側で管理者向けのサポート体制が整えられているのも特徴です。
企業としてはコスト削減と運営効率の両面から、必要回線数や運用方針に合わせたプランを選ぶことが重要です。
法人携帯ならではの独自特典を活用できるかどうかも、料金を最適化するポイントになります
- 基本料:1回線あたり1,000〜3,000円程度
- 端末代:分割払い(24〜36回)または一括購入
- オプション料:MDM、クラウドPBX、端末保証など
- 通信料:データ容量超過時の追加課金や通話料
また、回線数が10回線以上になると月額料金の割引率が高まるため、中小企業でも一定以上の規模があれば法人契約の方が安くなる場合があります。
👉詳しくは「法人携帯の料金体系を徹底解説」をご覧ください。
初期費用・月額料金の目安
導入にあたって最初にかかる費用と、毎月のランニングコストを把握することで、全体の予算計画が立てやすくなります。
法人携帯を導入する際の費用は、大きく分けて初期費用と月額料金の2種類に分けられます。
初期費用は端末購入や事務手数料など、契約当初に一度だけかかるコストです。一方、月額料金は基本使用料とオプション料金が中心となり、企業の運用スタイルによって変動します。
端末代金に関しては、一括で払う場合と分割払いを選ぶ場合があります。
大手キャリアのキャンペーンによっては大幅に割引が適用されることもあるので、契約時にはキャンペーン情報を確認するのがおすすめです。
キャリアの値引きや法人向けの特典を利用すれば、初期コストと月々の支出を抑えられる可能性があります。
ただ、必要以上にオプションを追加すると予想外に月額料金が高くなることもあるため、まずは会社の利用形態をしっかりと見極めておきましょう。
初期費用の内訳
初期費用には端末代金、契約事務手数料、場合によってはサーバやシステム接続に関するセットアップ費用などが含まれます。大手キャリアでは1回線あたり数千円程度の手数料がかかるのが一般的ですが、回線数や契約内容によっては免除や割引が適用される場合もあります。
端末代金はスマートフォンの機能やスペックにより大きく異なりますが、法人プランでは一度に複数台を購入するため、個人向けよりも割安に入手できるケースが多いです。
ただし、ハイスペック端末を導入するとコストが膨らむため、社用端末の目的に合ったレベルを選ぶようにしましょう。
- 事務手数料:1回線あたり3,000円前後
- 端末購入費:iPhoneの場合8〜12万円、Androidは5〜10万円程度
- 初期設定費用:1回線あたり1,000〜3,000円程度(外注時)
月額料金の目安(企業規模別)
小規模企業の場合、月額料金は1回線あたり数千円程度で収まることが多く、シンプルなプランで十分というケースが一般的です。業務で使用する通信量が限られている場合は、データ容量を抑えたプラン選択も検討するとよいでしょう。
一方で中規模以上の企業では、数十回線をまとめて契約することによる割引やデータ容量シェアプランなどを活用して、全体コストを下げる戦略が取られます。
通話重視なのか、データ通信重視なのかといった用途の違いによっても最適プランが変わるため、会社の利用実態を正確に把握する必要があります。
| 企業規模 | 平均回線数 | 月額料金(1回線あたり) |
|---|---|---|
| 大企業 | 100回線以上 | 2,500〜4,000円(割引率大) |
| 中小企業 | 10〜50回線 | 3,500〜5,500円 |
| 個人事業主・小規模 | 1〜5回線 | 4,000〜7,000円 |
大企業ほど回線数が多いためボリュームディスカウントが適用され、1回線あたりの単価が下がる傾向があります。
逆に小規模事業者の場合は、個人契約とあまり差が出ないこともあります。
👉詳しくは「法人携帯の初期費用・月額料金の目安」をご覧ください。
法人携帯に関する
お悩み・ご相談はお気軽に!
お客様の様々なニーズにお応えし、
ご利用に合う最適なプランをご提案します。
キャリア別法人携帯プラン比較
大手3キャリアと格安SIM事業者の法人プランを比較し、自社の運用スタイルにフィットした選択肢を探すことが大切です。
大手キャリアでは、回線数やデータ容量の多い利用を想定した法人プランが充実しており、複数回線契約での基本料金割引やデータシェアプランなど、さまざまな優遇措置があります。
たとえば、ドコモでは「ファミリー割引」や「みんなドコモ割」なども活用が可能で、法人割引と組み合わせればさらに料金を抑えられることもあります。
一方で格安SIM事業者も法人向けのプランを提供しており、通信費を大幅に節約できるのが魅力です。
ただし、大手キャリアと比べると通信品質やサポート体制で劣る場合があるため、コストだけでなく運用面も考慮する必要があります。
比較の際には、端末費用、サポート体制、通話品質、データ通信速度なども総合的に検討しましょう。
企業として重要な情報を取り扱う場合にはセキュリティもポイントになるため、各プランのセキュリティオプションや管理者向け機能も併せて確認すると安心です。
| キャリア | 月額基本料 | データ容量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| docomo | 3,500円〜 | 無制限・20GB・50GBなど選択可 | 法人向け管理ツールが充実、サポート手厚い |
| au | 3,300円〜 | 無制限プランあり | 地方でもエリアが広く、災害時の復旧が早い |
| SoftBank | 3,200円〜 | 50GBプランが人気 | テザリング無料、社内内線連携に強い |
| 格安SIM(MVNO) | 1,500円〜 | 3GB・10GBなど容量限定 | コストは安いがサポートは限定的 |
大手キャリアはサポートやネットワーク品質が強みですが、コスト重視ならMVNOも選択肢になります。
ただし、複数回線の一括管理やMDM連携を考えると、大手キャリアの法人プランの方が運用面では安心です。
業種別・用途別の料金パターン
会社の業務形態によって、最適なプランやオプションは大きく変わります。
同じ法人携帯であっても、営業中心の業種とデータ通信がメインの業種とでは必要となるコスト構造が異なります。
回線数の規模や使用頻度だけでなく、どのような通信手段を多用するかによって最適化の方法が変わるのがポイントです。
このセクションでは、代表的な業種や用途に合わせた料金パターンを紹介します。
ご自身の企業の利用状況を照らし合わせながら、費用対効果の高いプラン探しの参考にしてください。
営業・外回りが多い企業
営業担当者が外回りをする企業では、電話でのコミュニケーションが主になるケースが多く、通話定額やかけ放題プランを検討するとコストが安定しやすいです。
特に移動中に使用する機会が多いため、電波のつながりやすさもチェックポイントと言えます。
通話定額プランを導入したうえで、メッセージアプリなどを併用すると通信費を抑えながら顧客とのやり取りがスムーズにできます。
また、営業チーム全員で使用している回線の合計請求を月ごとに確認し、業務上の無駄がないか定期的にチェックすることも大切です。
IT・医療などデータ通信が多い企業
クラウドサービスや大容量ファイルのやり取りが頻繁に行われる業種では、データ通信量が多くなるため大容量プランや通信速度が速いプランの利用がポイントです。
映像や画像データ、オンライン会議などを多用する場合、通信速度の安定性も料金と同じくらい重視すべき要素ですよね。
格安SIMでも高速通信を提供している事業者がありますが、安定性やサポート面はやや劣る場合があります。
リモートワークやテレヘルスを行う現場ではトラブル対応の迅速さも求められるため、問題発生時のサポート体制やセキュリティオプションを含めて総合的に判断することが大切です。
事務中心の企業
通話やデータ通信の利用頻度がそれほど高くない事務中心の企業では、必要最低限のプランで十分な場合が多いです。
コストを最小限に抑えたいなら、通話が必要な部署だけかけ放題オプションをつけるなど、柔軟にプランを組み合わせるとよいでしょう。
オフィス内では通常Wi-Fi接続が可能なので、スマホのデータ通信量は少なくて済みます。
業務端末の導入メリットとしては、社内連携ツールの利用や社員間の通話料金が割安になるなど、細かな部分の経費を削減できる点も挙げられます。
請求予定金額の確認方法
月ごとにどの程度の費用がかかるかを把握し、予算オーバーを防ぐためには、請求予定額を定期的にチェックする習慣が欠かせません。
多くのキャリアではウェブ上のマイページや専用管理画面から現在の利用状況や請求見込み額を確認できる仕組みを提供しています。
例えば、ドコモの場合は「My docomo」を利用すれば、グラフ表示で全体の利用額やデータ通信量をスマートにチェック可能です。格安SIM事業者も類似の管理画面を提供しているところが増えています。
法人向けでは、管理者アカウントを使って複数回線の合計額だけでなく、部署ごと・個人ごとの利用状況を把握できる機能がある場合もあります。定期的に利用状況をチェックし、もし不必要なオプションや想定外の利用が見られるようであれば、速やかにプランを見直すことが大切です。
従業員が紛失などでログインできなくなった場面に備えて、PCからの確認方法も把握しておくとトラブル時にも安心です。特にパスワード管理や認証方式についてはセキュリティ強化が求められるため、企業全体の方針として統一しておくとよいでしょう。
| キャリア | 主な法人向け オンラインサービス |
確認方法の概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| NTTドコモ | My docomo(法人向け) ドコモビジネスメンバーズ |
ビジネスdアカウントでログインし、「料金」や「ご利用料金の確認」から請求予定金額(概算)や利用明細を確認できます。 過去の請求情報も閲覧可能です。 |
アプリでの確認も一部可能ですが、法人向けはWebサイトが中心です。 |
| au(KDDI) | au 法人サービス My au(法人向け) |
au Business IDでログインし、「ご利用料金」や「請求書・料金明細」といった項目から請求予定金額や利用明細を確認できます。 | 法人向け専用アプリを提供している場合もあります。 |
| ソフトバンク | 法人コンシェルサイト | 管理者IDとパスワードでログインし、「ご利用料金分析サービス」などから請求予定金額や内訳を確認できます。 | 請求確定時のメール通知設定も可能です。 |
確認時の注意点
- ログイン情報の準備: 各キャリアの法人向けオンラインサービスにログインするためのIDとパスワード(例:ビジネスdアカウント、au Business ID、法人コンシェルサイトのID)を事前にご準備ください。
- 概算表示: 請求予定金額は、締め日前の利用状況に基づく概算であることが多いです。最終的な確定金額は、締め日後に表示されます。
- 管理者権限: 法人契約の場合、請求情報の閲覧には管理者権限が必要な場合があります。一般の従業員では確認できないことがありますのでご注意ください。
- Webビリング: NTTグループの固定電話料金などと合算請求されている場合は、NTTファイナンスの「Webビリング」でも確認できることがありますが、携帯電話料金単独の場合は各キャリアのサイトが確実です。
その他、ご不明な点があれば、ご契約されているキャリアの法人サポート窓口へお問い合わせください。
法人携帯の料金削減・節約術
企業の経費削減につながる具体的なテクニックを押さえておくと、長期的に安定したコストコントロールが可能になります。
第一に、必要なサービスと不要なサービスを明確に分けることが重要です。
契約時に付けていたオプションが、実際にはそれほど使われていないケースも多くあります。定期的にオプションを洗い出して解約やプラン変更を検討するだけでも大きくコストを削減できます。
次に、複数キャリアを併用することでリスクヘッジとコスト最適化を同時に実現する方法も考えられます。
例えば、一部の回線を格安SIMで運用し、通話やサポートが重要な回線だけ大手キャリアにするなど、目的ごとにキャリアを使い分ける戦略です。
また、端末の運用年数を延ばすことで費用を抑える方法も有効です。新しい機種が出るたびに端末を買い替えると初期コストもかさんでしまうため、リースや端末保守サービスを活用しながら端末を長期利用することも検討するとよいでしょう。
- プラン見直し:利用実態に合わない大容量プランを適正化する
- Wi-Fi活用:社内や外出先でWi-Fiを活用しデータ通信料を抑制
- IP電話・クラウドPBX:社内内線通話をモバイル回線から切り離す
- 格安SIMの併用:コスト重視回線はMVNOを活用
- 共同回線契約:グループ会社や取引先とまとめて契約し割引適用
さらに、利用状況のモニタリングやMDM導入による利用制限で、無駄な私用利用による料金増加も防げます。
👉詳しくは「無駄を徹底的にカットする方法」をご覧ください。
料金トラブル・注意点
法人携帯導入後によく起こる料金に関する苦情やトラブルを回避するには、あらかじめ注意点を把握しておくことが大切です。
一つの例として、通話やデータ通信の超過料金が予想以上に膨らんでしまうケースがあります。
営業マンが集中して外回りを行う月など、利用が増えるタイミングを見越してプランを調節する仕組みが大切です。
また、利用実態と異なるプランを契約したまま放置してしまうケースも見受けられます。大企業では部署単位で料金のチェックが曖昧になることが多く、余分なオプションが付いたままになっていないか定期的に確認することが求められます。
さらに端末の紛失や故障時の対応策もトラブル回避の要です。保険や補償に加入していないと、高額な修理費用や端末再購入費用が発生する可能性があります。早期発見・早期対処のためにも、管理ルールや保守体制を整えておきましょう。
- 契約期間・解約金:法人プランは2〜3年契約が基本。
途中解約すると回線数×9,500円程度の違約金が発生する場合があります。 - 端末残債:分割払いの場合、解約時に残りの端末代を一括請求されるため要注意。
- 社員の私用利用:動画視聴やゲームなど業務外利用でデータ容量が超過し、追加料金が発生するケースが多いです。
これらを防ぐには、契約時の条件確認を徹底し、MDMなどの管理ツールを活用して業務外利用を制限する仕組みが重要です。
👉詳しくは「よくある落とし穴と賢い回避法」をご覧ください。
料金と導入メリットのバランス解説
費用だけに注目するのではなく、導入による効率化やセキュリティ強化といった付加価値とのバランスを取ることも大切です。
法人携帯は、ビジネス上の連絡をスムーズに行うためのインフラとして非常に重要な役割を担います。
料金の安さを重視して最低限の機能しかないプランを選んでしまうと、現場でのトラブル対応やコミュニケーションスピードが低下するリスクも生じます。
一方で、必要以上に高機能なプランを選び続けると、毎月の固定費がかさみ、企業経営に負担をかける原因にもなります。
そのため、導入メリットと料金の両面を踏まえて総合的に判断することが望ましいでしょう。
社員の業務効率が向上することで得られる利益や、セキュリティ体制を強化することで回避できるリスクといったプラス面も考慮することで、より適切な料金プランを選択できるはずです。
- セキュリティ向上:情報漏洩リスクを減らし、コンプライアンスを確保できる
- 業務効率アップ:社内システムや内線との連携で移動中も業務可能
- 経費処理が明確:業務利用分を正確に経費計上できるため、税務リスクも軽減
短期的にはBYODの方が安価に見えますが、長期的に見れば法人携帯導入の方がトータルコストを抑え、リスク回避にもつながるケースが多いです。
長期利用での総コストシミュレーション
法人携帯の費用は長期的な視点で見ると、利用年数や回線数によって大きな差が生まれます。
短期間だけを見て安いプランを選ぶと、後々の運用で思わぬコスト増が起きることもあります。
逆に、長期契約を前提に割引を適用して抑えられるケースもあり、一概にどちらが得とは言えません。
ここでは、代表的なシミュレーション例をいくつか挙げて、総コストをイメージしやすくするためのモデルを解説します。
企業の成長や業界の変化も加味しながら、将来的な運用スタイルに合わせてプランを選定するのが重要です。
10回線×3年間の場合
仮に10回線を3年間利用するケースを考えると、端末代金の支払い方法と月額プランの組み合わせで総コストが大きく変動します。
例えば、3年間の分割払いを選ぶと、端末費用の負担は毎月少額で済みますが、途中で故障や紛失があると新たに支出が発生する可能性があります。
通信プランは通話定額とデータシェアプランを組み合わせることで、月額料金を安定させられます。
導入初期は想定より通信量が多い部署と少ない部署があることが一般的なので、定期的に利用状況を見直してプランを最適化することがポイントです。
- 初期費用:端末代(iPhone 10台×10万円)+事務手数料3,000円×10回線=約103万円
- 月額費用:1回線5,000円×10回線=5万円/月 → 3年間で180万円
- 合計:約283万円
BYOD運用と比較した場合
社員が自分のスマートフォンを業務で使用するBYODは、会社として端末費用を負担しないので一見コスト削減につながりそうにも見えます。
ですが、セキュリティリスクやデータ管理の煩雑化など、運用面の問題が増える点に留意しましょう。
法人携帯を支給する場合は初期費用や月額料金を企業が負担する一方で、デバイス管理やセキュリティ対策がしやすくなります。
どちらが安いかは企業の業務内容やセキュリティポリシーによるため、単純な費用比較だけでなく、運用負荷やリスクも考慮した総合判断がおすすめです。
オプション込みの場合
端末保険やセキュリティ強化オプションなどを付けると、月額料金は上乗せになりますが、故障や情報漏洩が発生した場合のリスクが軽減されます。
特に、持ち出しが多い部署や外部からのアクセスが多い企業では、オプション費用をかける価値があります。
オプション料金は少額でも積み重ねるとそれなりの出費になりがちです。
ただし、リスク回避によって結果的に大きなコストセーブにつながることを考えれば、長期的に見ると合理的な投資になる場合もあります。
料金管理と経費処理のポイント
法人携帯の利用料金は毎月発生する経費として処理されるため、正確な管理とスムーズな経理対応が求められます。
まず、部署や担当者ごとに回線の利用実態を把握し、請求書との突合を行う仕組みを確立することが重要です。
社内で締め日を揃えたり、管理画面を利用して消費データを定期的に共有する運用を導入すると、経理担当者の負担が軽減されるでしょう。
また、税務上の扱いとしては、通信費やリース料として仕訳を行うケースが多いです。
業務利用を明確化することで、法人税の申告にも対応しやすくなります。
複数拠点で運用している場合は、どの拠点の利用がどれだけ発生したかを明確にしておくと、経費予測や分析にも役立ちます。
さらに、導入後にプラン変更や端末更新をする際には、追加で発生する回線開設費用や事務手数料などを見落としがちなため、常に最新の料金表を確認しておくことが大切です。
- 勘定科目の選択:通信費・リース料・福利厚生費など、用途に応じた仕分けが必要
- 請求書・明細の管理:電子帳簿保存法に対応する形で保存するのが望ましい
- コスト見直し:定期的に利用状況を分析し、不要な回線やプランを整理
最近ではクラウド型の料金管理ツールを導入する企業も増えており、効率的に管理できる環境が整いつつあります。
法人携帯の料金に関するよくある質問
検討段階で抱きがちな疑問や不安を解消し、導入をスムーズに進めるための「よくある質問」をまとめました。
複雑に見える法人携帯の料金体系ですが、基本的な疑問点を理解しておくことで、より正確なコスト試算やプラン選定が行いやすくなります。
また、キャリアごとに適用条件が異なるため、公式サイトや営業担当に確認して最新情報を入手することがとても大切です。
契約前に疑問や不安を解消し、納得できる状態で導入を進めましょう
ここでは、多くの企業が気にする代表的な質問を取り上げます。
Q1. 何回線から法人割引が効きますか?
多くのキャリアでは、少ない回線数でも一定の法人割引が適用されるケースがあります。
例えば数回線の契約からでも、基本料金の一部が割引になることもあるため、導入時にはキャリアの担当者に具体的な回線数を伝えて確認するようにしましょう。
また、契約の総額やデータ通信量によって適用される各種プランや割引内容は変わってくるため、見積もりは複数社から取り寄せて比較検討すると最適なプランに近づきやすいです。
Q2. BYODとどちらが安いですか?
BYODであれば端末費用が企業負担にならない分、確かにランニングコストを抑えられる可能性はあります。
しかし、個人の端末を業務で使うことでセキュリティ面の対策が難しくなったり、通信費の精算が煩雑になるケースがあります。
法人携帯の場合は毎月の通信費が発生しますが、明確に業務利用として経費処理しやすくなり、端末の管理やセキュリティ設定を統一できるメリットがあります。
コストと運用リスクのどちらを重視するかで判断が変わるため、自社の業務要件に合わせて選択すると良いでしょう。
Q3. 税務上の扱いはどうなりますか?
法人携帯の料金は一般的に通信費として計上でき、リース契約の場合はリース料として計上します。
いずれの場合も業務利用を明確にしておけば、法人税申告などの際に経費扱いされます。
個人利用と業務利用の線引きをはっきりと区別しておくことが重要で、社内規定や使用ルールを明文化しておくとトラブルや指摘を受けにくくなります。
まとめ|法人携帯料金はコストではなく投資
法人携帯の導入によって得られる利便性や業務効率の向上は、長期的に見ると企業の発展に貢献する重要な要素となります。
料金だけを見て判断すると、短期的な節約にはなっても必要な機能やサポートを得られない可能性があります。
一方で、過剰なオプションを付けすぎれば、かえってコスト負担が大きくなります。
大切なのは、自社の業務内容やセキュリティポリシーに合ったプランを選び、長期的な視点でコストとメリットのバランスを検討することです。
法人携帯を「余分なコスト」と捉えるのではなく、「業務を円滑に進めるための投資」として考えることで、より最適な導入が実現できるでしょう。
👉法人携帯ドットコムの法人向け特別価格については「法人向け携帯の各種料金プラン」をご覧ください。