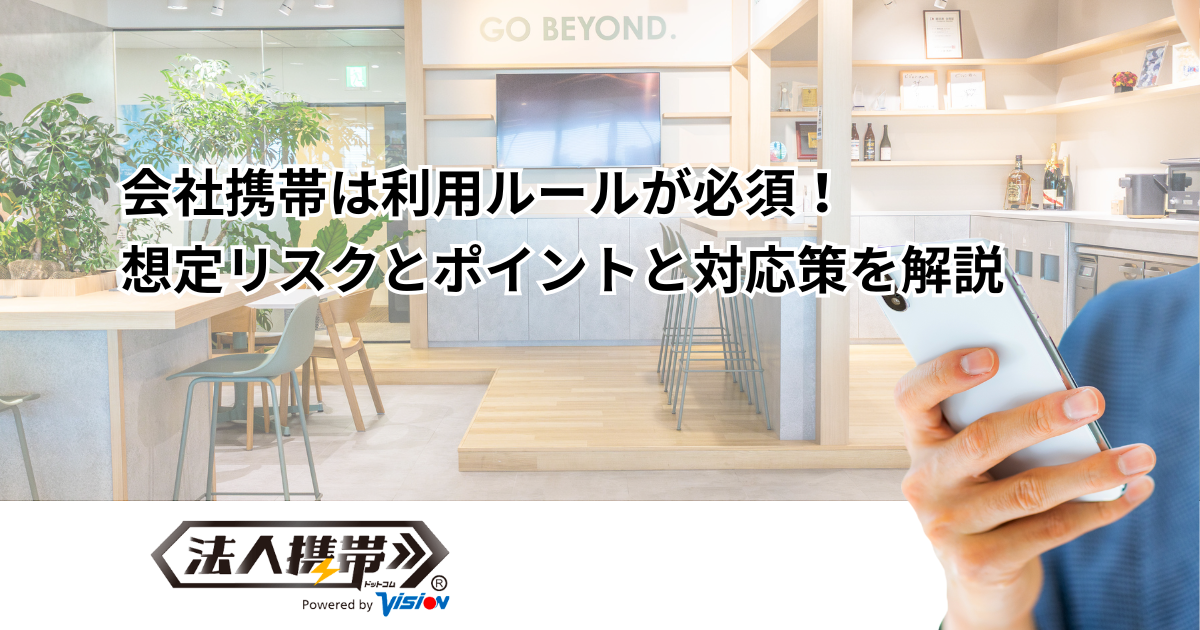目次
ビジネスでは、顧客情報や取引先情報など重要な情報を取り扱う場面が多々あります。
そのため、機密情報の漏えいなど重大な情報事故に遭うリスクがあります。
そこで、本記事では、会社携帯を利用する上で想定されるリスクとそのリスクを回避するための利用ルールやルール制定時のポイントについて解説していきます。
企業で携帯電話を管理する必要性とは?
法人携帯として会社が社員に携帯電話を貸与する場合、様々な制約を設けておく必要があります。
社用以外での使用ができないように通話記録などの管理を行ったり、業務に不要なアプリをインストールできないようにしたりするなど、個人のモラルにかかる部分もありますが、社内規定である程度規制をしていくのがいいでしょう。
また、法人携帯を導入するにあたって、意外に複雑化しやすい事務処理に関しても、キャリアを統一したりするなどの工夫が必要になります。
部門や部署毎に異なる法人携帯となると、事務処理が大変になってしまうので、こちらも留意しておきましょう。
運用にあたっては、きめ細かいルール作りが必須になり、紛失や盗難に関しての然るべき対策を講じておく必要があります。
携帯電話の電話帳に入っているデータを悪用されないようにするために、ロックをかけたり遠隔操作によるデータ消去などができるようにしておくなど、キャリア毎に行われているセキュリティ管理のサービスを有効活用していくのが良いです。
機種にもよりますが、「GPSによる位置検索」や「MDMツールによる遠隔操作」もできるようにもなっているので、適切な使用がなされているか監視する体制も必要になってきます。
会社・業務用携帯の需要拡大
ウィズコロナ・アフターコロナに向け、急速にデジタル化・テレワークが進んでおり、会社・業務用携帯としてスマホ(スマートフォン)の需要がかなり高まっています。
ミライのお仕事の調査によると、成人男女500名に対して、「テレワークを導入できているか」を調査。
結果として、約70%の人は「以前と働き方は変わっていない」と回答。
「週に3回以上テレワークになった」と回答した人は、わずか14%。
東京都のみに絞ると、同回答は28.6%にまで上がる。株式会社ネクストレベル(本社所在地:神奈川県横浜市、代表取締役:田中大洋)
ミライのお仕事「テレワーク・リモートワークの現状について調査」
個人携帯の業務利用について
このような急激な環境変化により会社・業務用携帯端末の準備が追いつかず、個人のプライベート端末を代用する「BYOD(Bring Your Own Device)」を取り入れる企業も多数見受けられます。
BYODとは、従業員のプライベートな携帯端末を業務に取り入れることを意味します。
BYODはプライベートとの併用となるため端末管理が難しく、情報漏えい事故などセキュリティ面に大きな課題があります。
そのため、一括管理が可能な法人携帯を業務用デバイスとして利用されることを推奨いたします。
BYODについては「BYOD完全ガイド|企業が個人端末を安全に業務利用するための全知識」をご覧ください。
法人携帯に関する
お悩み・ご相談はお気軽に!
お客様の様々なニーズにお応えし、
ご利用に合う最適なプランをご提案します。
法人携帯の利用メリット
企業における法人スマホ導入のメリットとしては、社内外の円滑なコミュニケーションを可能にするだけでなく、
アプリの活用などによる業務効率の改善が図れる点が挙げられます。
特に、外出の多い業種では、
- 外出先から会社の番号を使って発着信をしたい
- 時間を効率的に使いたい
- 資料の確認を外出先から行いたい
などといった声を多くお聞きします。
法人スマホの導入で、これらのご利用ニーズをすべて解決することができます。
一方、法人スマホ導入のリスクももちろんあります。
法人スマホ導入の一番大きなリスクとしては、管理不行き届きによる情報漏えいが挙げられます。
企業の情報漏えいは年々増加傾向にありますが、機密情報などの重要な情報は一度でも流出してしまうと企業にとって甚大な被害になります。
社内で明確に利用ルールを設定し、かつ誰が見ても分かりやすく、周知のしやすい形で作成することで人為的なミスで発生する情報漏えいを未然に防ぐことが可能です。
このように、企業における法人スマホの導入はうまく活用すれば従業員の生産性向上につなげられますが、しっかり管理をしないとセキュリティ面でのリスクを伴うため利用ルールの設定・徹底が重要となります。
法人携帯の利用目的とは
まず、法人携帯とは、会社で利用する携帯電話(ガラケーやスマートフォンなど)を法人契約で利用することを指します。
そして、法人携帯の主な利用目的とは、業務連絡や情報共有が挙げられます。
法人ガラケーを導入される場合は、主に「外出先から通話をしたい」、「なるべく通信費を抑えたい」といった目的で導入されるケースがほとんどです。
そのため、法人ガラケーを利用される場面では、業務連絡や顧客との連絡に利用されます。
法人スマホと比較すると、毎月の通信コストを抑えることができるため、シンプルに通話のみを求めている方におすすめしています。
法人スマホを導入される場合は、主に「外出先から会社の番号を使って通話をしたい」、「スマホアプリを使いたい」といった目的で導入されるケースが多いです。
そのため、法人スマホを利用される場面では、業務連絡・顧客との連絡の他に、カメラ機能やスマホ内線化などのアプリの活用など業務効率改善のため利用されます。
携帯ショップなどで個人契約される場合と比較すると、法人スマホは毎月の通信コストを抑え、かなりお得にご利用いただくことが可能です。
アプリやツールを一緒にご利用いただくことで、ご利用ニーズへの対応やコスト削減が可能となる場合が多数ございます。
法人携帯の導入によるメリット
法人携帯の導入によるメリットは、大きく2つが挙げられます。
コミュニケーションの活性
オフィス・店舗間のコミュニケーションに特化したビジネスチャットツールを活用することで、画像やファイル共有などリアルタイムで情報共有が可能となり、社内のコミュニケーション活性につながります。
メールや電話でのやり取りでは意思疎通の欠如やすれ違いから業務の進行に遅延や問題が発生する場合があります。
一方、ビジネスチャットツールではリアルタイムにやり取りが可能で、かつテキストでのコミュニケーションとなるため認識相違なく円滑に業務を進めることができます。
また、ビデオ通話機能を搭載しているツールであれば、オンライン会議も可能となるためテレワークや一時的な在宅勤務などといった場合にも対応が可能です。
アプリの活用による業務効率改善
法人スマホならではのメリットとして、勤怠管理やスマホ内線化アプリなどを利用することで従業員の業務効率改善につながります。
クラウド勤怠管理システムでは、ご利用の法人スマホやタブレットにアプリをダウンロードするだけで外出時などどこでも出退勤申請が可能となります。
また、直行直帰が多い職種の場合、不正打刻を心配されるケースがありますが、位置情報機能と連携しているクラウド勤怠管理システムなら不正防止にもつながります。
法人携帯ドットコムではこのような法人・個人事業主様に便利なソリューションもご提案が可能です。
「コスト削減をしたい」、「社内の生産性をアップしたい」などといったご利用ニーズに合わせて柔軟にご対応いたします。
使用状況と使用方針を明確にする
法人携帯の使用に関して、その使用目的に沿った使い方をしていくことが求められます。
社内規定でしっかりと定めておくのはもちろんのこと、導入に際してはきちんとした社内教育を徹底するなど、意識統一を図ることが前提です。規定に違反した場合の罰則や、紛失・盗難が発覚した時の連絡手順や、事後処理などの緊急措置についても明確にしておきましょう。
業務場での使用についてどういったケースでの使用が望ましいかということを明示しておき、私的利用ができないようにすることが必要です。
使用に際してのモラルを当然守ることも会社の顔として活動する社員に求められてくるので、そうした一般的なルールに関しても規定を作っておくのが良いでしょう。
規定に関しては他の企業のものをそのまま流用してしまうということも少なくないようですが、運用については状況別の使用規定や、方針について細かく話し合った上で、社内での使い方に合ったものを策定していくのが望ましいです。
法人携帯の管理不十分によるリスク
上記でお伝えしたように従業員の生産性向上を目的とし、法人携帯を導入し社員に貸し出しをした場合でも管理不十分により会社携帯を私物化されると会社としてはコストがかさむだけとなります。
そのため、法人携帯の導入を成功させている多くの企業では、会社携帯の管理体制を徹底し、社内規定の中に会社携帯の利用ルールを設けています。
法人携帯の導入前にどのようなリスクが想定されるのか、リスク対策はどう取り組むべきなのかをしっかり把握し対応する必要があります。
会社携帯を私物化することによるリスク
従業員が会社携帯を私物化することで、コスト面・セキュリティ面でのリスクが考えられます。
コスト面で見ると、法人携帯の契約プランによっては、利用した分だけ費用が発生する従量課金制等の場合、通話料やインターネット利用料などで想定よりもコストがかかるケースもあります。
そして、通信コストよりも気になるのがセキュリティ面です。
主なセキュリティ面でのリスクは、
- 脆弱性が指摘されるフリーWi-Fiの利用による通信の盗み見
- セキュリティ対策のされていないスマホを踏み台とした社内ネットワークへの侵入
- 有害アプリのダウンロードによるウイルス感染
などが挙げられます。
社内で利用ルールが明確に設定されていないと、利用する社員によってセキュリティ対策への意識・効果は異なります。
私物化され業務に不必要なアプリのインストールや有害サイト・メールの閲覧をすることで、ウイルスに感染し情報漏えいや不正アクセスなどの危険性が考えられます。
このようなセキュリティのトラブルは、会社にとってとても大きな影響を与えることとなります。
そのため、会社携帯はあくまでも業務上の連絡手段としての貸し出しであることを周知させる必要があります。
業務上に必要な機能のみに制限することも一つの手段と言えます。
会社携帯の紛失によるリスク
会社携帯は業務に利用するため、社内だけでなく、取引先の情報など機密情報が多く含まれます。
主な会社携帯の紛失時のリスクは、
- 会社携帯紛失時のデータ流失による情報漏えい
- 競合他社などへの機密情報の持ち出し
などが挙げられます。
そのため、会社携帯の紛失は情報漏えいに繋がる恐れがあり、また、代替え端末の手配により不要なコストもかかります。
こういったリスク対策から会社携帯の紛失を防止する目的で、ストラップの利用を義務付けるケースもあります。
法人携帯ドットコムでは、紛失時の対応も電話1本で対応しており、遠隔操作によって情報漏えい防止のため該当端末にロックをかける対応をしています。
また弊社独自のサービスとして、紛失・故障時の代替え端末を最短即日、無料で手配が可能な安心補償サービス「ガラサポ」をご提供しています。
すでにご利用いただいている携帯端末にも適用可能なため、補償サービスに関するお問い合わせも可能です。
お気軽にお問い合わせください。
会社携帯を紛失した時の対象方法については「会社携帯の紛失を防ぐポイントとなくしてしまった際の対処法」をご覧ください。
貸与する際はルールを決めることが大事
当然のように会社の携帯電話として貸与する場合には、会社の決めたルールに従って使用されなければなりません。
私的利用はもちろんのこと、業務外での使用に関しても罰則を設けるなどして、然るべき規定を作成しておくことが重要です。
また、そうしたルールがあるということを、使用する社員に対して教育していくこともポイントになります。
利点の多い携帯電話だからこそ、私的なことに使ってしまいがちになるという事もあるので、その点に関しても強く意識させておきましょう。
法人携帯の運用にあたっては、管理部門を設けて各携帯が適正に使用されているかをチェックすることが必要になってきます。
会社の規模が大きくなればなるほど、こうした管理体制が重要な役割を担ってくるのです。
法人携帯の利用ルール設定のポイントのまとめ
上記で法人携帯導入時のリスクについて触れましたが、リスク対策のための利用ルールは設定することがゴールではなく、
徹底した利用ルールの周知と順守がとても重要となります。
そのため、利用ルールの設定時は可能な限りわかりやすくする必要があり、定期的な運用状況のチェックも大切となってきます。
私用目的での利用は禁止にする
会社携帯の私物化を防ぐため、貸し出しする携帯端末の私用目的での利用は禁止にすることをおすすめいたします。
会社携帯は会社の財産となるため、私的利用した場合懲戒処分等の対応に該当する事項でもあるためです。
会社携帯に発生する費用は経費として出ていくお金のため、会社側でしっかりと管理する必要があります。
使用目的での利用をさせないためにも利用ルール、会社規定にその旨を明記しておきましょう。
業種によって、細かい利用ルールは異なります。
例えば運送業や建設業、派遣サービス業など働く場所が固定されていない業種の場合、GPS機能の利用を会社規定に記載している会社もあります。
どういったルール、規定を設定するべきかお悩みの方はお気軽にご相談ください。
会社携帯の休日利用については「会社携帯を休日で使うことへの是非|トラブル防止のルールと実務対応ガイド」をご覧ください。
定期的な運用状況のチェックを行う
法人携帯の導入を成功させるためには、利用ルールを明確にし設定することが重要であるとお伝えしましたが、しっかり社内で利用ルールに沿った運用がされているのかどうかを確認することも重要です。
周知をしっかり行うためにも、従業員全員が利用ルールを把握しており、すぐに確認できるように環境を整えることも大切です。
そのために年に1回~数回程度、利用ルールの確認テストなどを行うことで、周知の徹底に取り組むことも有効的です。
利用ルールと合わせて実際の事故・紛失事例を都度共有することも従業員の危機感を高めるのに効果的です。
利用ルールを破った場合
罰則の内容を会社規定に記載しておくことも利用ルールを順守させる上で効果的と言えます。
利用ルールの確認の他に、定期的な利用状況の確認を行うこともセキュリティ対策として効果的です。
例えば、「普段利用する通話先とは異なる電話番号への受発信がある」場合、競合他社などへの機密情報の流出の可能性が考えられます。
もちろん、営業部などでは新規顧客など多くの電話番号への受発信が発生するかと思いますので、業種などにより異なります。
会社で会社携帯の利用状況をモニタリングをしている事実を従業員に周知しておくこと自体が、リスク対策に繋がる場合も多いため推奨いたします。
通話料の把握と精算を管理する
基本的なことですが、会社の携帯として運用していくにあたっては、維持管理のコストとして通話料金が発生してきます。
使用していなくても基本使用料はかかってくるので、導入した数は適正かどうか、契約したプランで問題ないかを随時吟味しながら運用していくことが必要です。
また、個人の携帯電話を業務に使用せざるを得なくなった時にも、その時に発生した通話料などの料金について精算する仕組みを整えておくと良いでしょう。
個人の携帯電話を業務に使用(BYOD)した際の通信費を巡ってトラブルになったケースもあるので、少額でも精算していくように取り決めを作っておくのが良いです。
一般的には、一律の金額を支給するケースが多く、社員からの申請を元に実費精算するというところもあります。
セキュリティ対策を行う
法人携帯は紛失した時などに考えられる情報漏えいのリスクを考えると、会社で管理することが理想的です。
会社で管理している企業様にお話をお伺いすると、
- 会社の就業時間のみ法人携帯を配布している
- 業務終了時に責任者により回収し管理している
という回答をいただく場合があります。
このように、その都度携帯電話の配布・回収をして管理をする場合、責任者の方の負担が大きく面倒な業務が増えることとなります。
一方、会社携帯を従業員個人に管理を任せている企業様の場合、「利用方法などの契約を交わして社員に利用させている」という回答をいただくことが多いです。
個人に管理を任せた場合、管理を行う責任者側の負担はないですが、会社で管理をする場合と比較すると紛失などのリスクは高まります。
個人に管理を任せていても、会社携帯の利用に不必要なサービスには制限をかけることで、セキュリティ対策・リスク対策を行うことができ、セキュリティ対策のためのオプション機能以外でも、
- 携帯電話にパスワードロックをかけることを必須とする
- 紛失時の対応をマニュアル化する
など、社内で対策することも可能です。
このように法人携帯の導入にはセキュリティ対策を合わせて行うことがとても重要となります。
法人携帯ドットコムでは、法人携帯の導入のサポートとしてセキュリティ対策や活用方法のご提案も行っております。
法人携帯のセキュリティ対策|リスクと管理方法を徹底解説についてはこちら
法人携帯に関する
お悩み・ご相談はお気軽に!
お客様の様々なニーズにお応えし、
ご利用に合う最適なプランをご提案します。