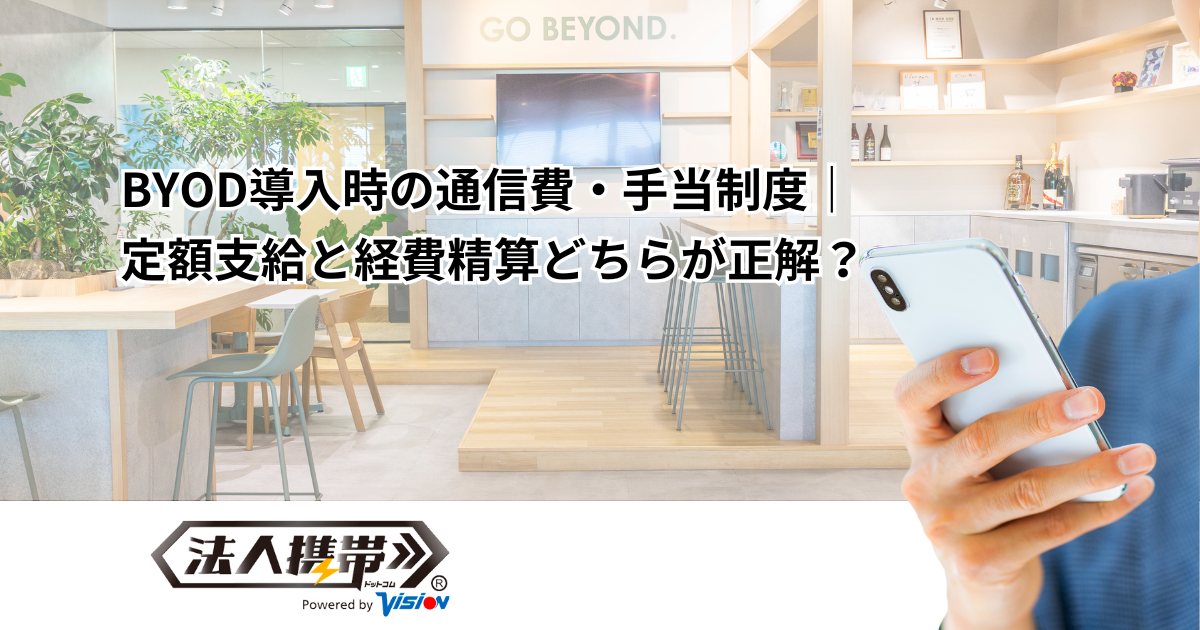目次
BYOD(BringYourOwnDevice)を導入する企業が増加する中、必ず検討すべきなのが「従業員の通信費や端末費用をどう補助するか」という問題です。
制度が曖昧なまま導入を進めると、不公平感やトラブルにつながりかねません。
本記事では、代表的な補助制度である「定額支給」と「経費精算」の違いやメリット・デメリット、選定のポイントを詳しく解説します。
BYODにおける通信費・端末費の補助が必要な理由
BYODでは、従業員が自らのスマートフォンやPCを使って業務を行うため、当然ながら通信費や端末代の一部が業務起因となります。
企業側がこの費用を一部補助することで、従業員の不満を防ぎ、継続的な利用を促進できます。
- 業務使用による通信量の増加
- アプリやクラウド利用に伴うデータ使用
- 業務目的での機器グレードアップや買い替え
これらの点を放置してしまうと、従業員側に過剰な負担感が生じ、生産性やモチベーションの低下にもつながります。
定額支給制度の特徴とメリット・デメリット
「毎月●円をBYOD手当として支給する」という形式が、定額支給制度です。
業務実態にかかわらず定額を支給するため、企業・従業員ともに管理の手間が軽減されるという特徴があります。
- メリット:管理が簡単・給与と一括処理できる・従業員にとって予測可能
- デメリット:実態と乖離しやすい・使用が少ない従業員にも支給が発生
公平性よりも運用のシンプルさを重視する企業や、支給額をあらかじめ予算化したいケースに適しています。
法人携帯に関する
お悩み・ご相談はお気軽に!
お客様の様々なニーズにお応えし、
ご利用に合う最適なプランをご提案します。
経費精算制度の特徴とメリット・デメリット
実際に発生した費用を領収書や使用明細に基づいて精算する方式です。
より業務実態に即した補助が可能ですが、管理工数がかかる点に注意が必要です。
- メリット:支出の根拠が明確・業務使用に即した支給が可能・不正防止
- デメリット:毎月の申請・承認フローが煩雑・個別対応の工数が増える
特に在宅勤務が多く、通信費の業務割合が高いケースでは、精算方式の方が納得感が得られる傾向にあります。
社用携帯・私用携帯の経費処理については「法人携帯は経費で落とせる?処理方法・勘定科目・注意点を完全解説」をご覧ください。
どちらが正解?企業規模・業務形態ごとの選び方
定額支給と経費精算、どちらが適しているかは企業規模や業務スタイルによって異なります。
以下の表を参考に、自社の状況に合った制度を検討しましょう。
- 中小企業(従業員数100人以下):定額支給が主流。人事・経理リソースが限られているため簡易運用が優先されやすい。
- 大企業・全国展開型:精算方式を採用する企業が多い。社内システムで自動申請・承認フローが整っている。
- テレワーク中心企業:精算方式が有利。使用実態に合わせた支払いが重要になる。
一方で、制度のハイブリッド化(基本は定額+高額利用時は精算)という選択肢も現実的です。
通信費制度を設計する際のチェックポイント
制度を整備する際は、単なる支払い方法だけでなく、
「税務」・「労務」・「社内ルール」との整合性を意識することが大切です。
以下のチェックリストを活用してください。
- 給与扱いor非課税扱いの判定(税務署への確認含む)
- 就業規則・給与規定への明文化
- 従業員への制度説明と同意取得
- 管理部門の工数・承認体制の確認
- 制度導入後の運用改善フィードバック制度
特に税制上の取り扱いは、課税対象となるかどうかで従業員の手取り額に影響するため慎重な設計が求められます。
まとめ|従業員も企業も納得できる制度設計を
BYOD制度を成功させるには、「業務の利便性」と「従業員の公平性」を両立させることが必要です。
通信費や端末費用に対する補助制度は、そのバランスを保つための重要な施策となります。
今回紹介した2つの制度の違いや選び方、設計時の注意点を踏まえ、御社に最適な制度を構築しましょう。
👉BYODの運用においては、通信費・端末費用の補助制度だけでなく、セキュリティ対策やポリシー整備など、幅広い観点での準備が求められます。詳しくは「BYOD完全ガイド」をご覧ください。
法人携帯に関する
お悩み・ご相談はお気軽に!
お客様の様々なニーズにお応えし、
ご利用に合う最適なプランをご提案します。