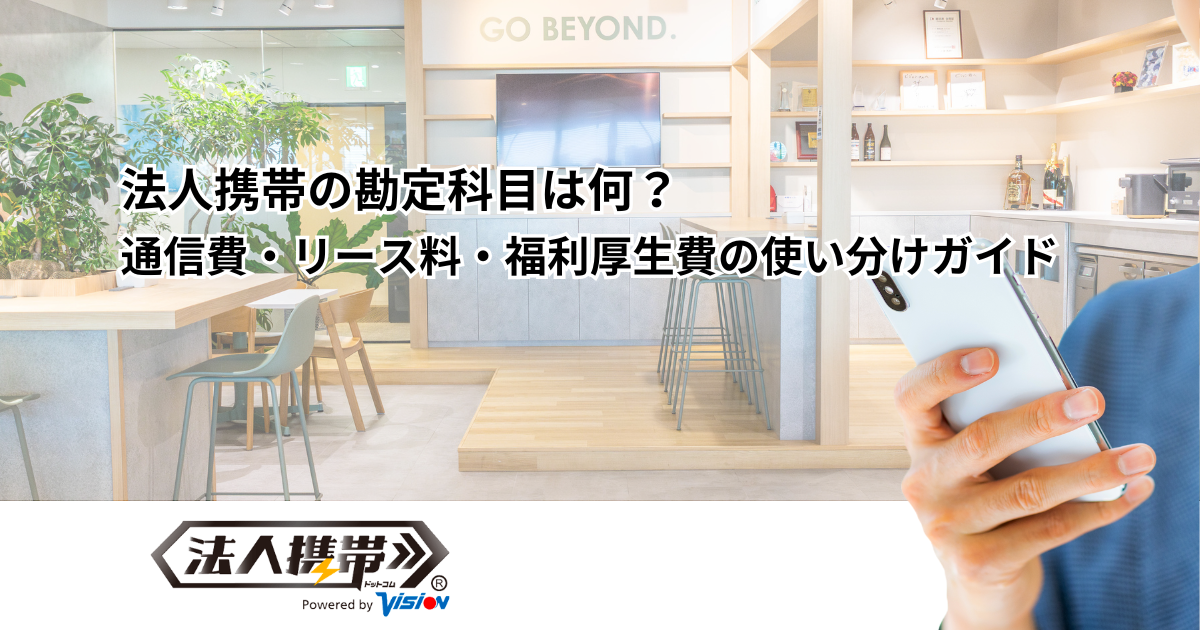目次
法人携帯を導入した際、「この費用はどの勘定科目で処理すればいいのか?」と悩む経理担当者は多いのではないでしょうか。
法人契約のスマートフォンは、通信費や端末代、管理ツールなど費用項目が多岐にわたるため、適切な勘定科目の選定が必要です。
本記事では、法人携帯にかかる費用の内訳から、勘定科目の使い分け、仕訳例、注意点まで、税務リスクを回避しつつスムーズに経費処理を行うための実務ガイドをお届けします。
法人携帯にかかる費用の内訳とは?
法人携帯の費用は、端末代や通信料だけでなく、導入方法や管理体制によって多様な項目に分類されます。
以下は代表的な費用構成です。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 端末代 | スマートフォン本体の購入費用(分割・一括・リース) |
| 通信料 | 月額の通話・データ通信料金(キャリアとの契約) |
| 管理費 | MDM(モバイル端末管理)などのセキュリティ・管理ツール利用料 |
| 補償・保守料 | 故障時のサポート費用や保険料 |
| 社員向け利用費 | 福利厚生目的で貸与される場合の費用(私用含む) |
これらの費用は、それぞれ異なる性質を持つため、勘定科目も適切に使い分ける必要があります。
次章からは、代表的な勘定科目とその判断基準を見ていきましょう。
勘定科目の基本|法人携帯はどの科目で処理する?
法人携帯にかかる費用の処理にあたっては、以下のような勘定科目が使用されるケースが一般的です。
- 通信費:月額の通話料・データ通信費(基本)
- リース料:端末をリース契約で導入した場合の月額支払い
- 消耗品費:端末を一括購入し、10万円未満である場合
- 固定資産/減価償却費:10万円以上の端末を購入し、資産計上する場合
- 福利厚生費:社員の私用を含めた使用が認められている場合
- 支払手数料:MDMやクラウドサービス利用料など
勘定科目は「正解が1つ」というよりは、「費用の性質」に応じて選択するものです。
同じ携帯電話代でも、導入方法や利用目的が違えば科目も異なります。
法人携帯に関する
お悩み・ご相談はお気軽に!
お客様の様々なニーズにお応えし、
ご利用に合う最適なプランをご提案します。
利用目的別の勘定科目分類(ケース別早見表)
以下の表は、法人携帯の利用目的や契約形態ごとに、推奨される勘定科目を整理した早見表です。
経理処理時の参考としてご活用ください。
| 利用ケース | 想定される内容 | 推奨勘定科目 |
|---|---|---|
| 営業社員に貸与し、業務通話・連絡に使用 | 通話・通信がメイン | 通信費 |
| 端末を一括購入(1台8万円) | 消耗品として扱える金額 | 消耗品費 |
| 端末を一括購入(1台15万円) | 固定資産として登録 | 工具器具備品・減価償却費 |
| MDM(モバイル管理)ソフトを月額導入 | クラウドサービス使用 | 支払手数料 |
| 福利厚生目的で全社員に携帯貸与(私用OK) | プライベート利用を含む | 福利厚生費 |
| キャリアとリース契約(2年縛り) | 分割で端末代を支払 | リース料 |
特に、福利厚生費や減価償却の扱いは、税務上の扱いにも影響するため注意が必要です。
次章では、より具体的な仕訳例を見ていきましょう。
仕訳の具体例|こんなとき、どう処理する?
ここでは、実際の経理処理でよくある法人携帯の仕訳例を紹介します。
用途や契約形態ごとに、適切な勘定科目を使って処理しましょう。
(1)業務用スマホの月額利用料
【借方】通信費 10,000円 【貸方】普通預金 10,000円
(2)端末を一括購入(8万円)した場合
【借方】消耗品費 80,000円 【貸方】普通預金 80,000円
(3)端末を一括購入(15万円)した場合
【借方】工具器具備品 150,000円 【貸方】普通預金 150,000円 ※減価償却の対象になります。
(4)MDMの月額利用料を支払った場合
【借方】支払手数料 3,000円 【貸方】普通預金 3,000円
(5)社員に私用も許可した法人携帯を支給
【借方】福利厚生費 12,000円 【貸方】普通預金 12,000円
(6)端末リース契約(分割払い)の場合
【借方】リース料 5,000円 【貸方】普通預金 5,000円
※上記は一般例です。実際の仕訳は会計ソフトの仕様や税理士の判断によって異なる場合があります。
勘定科目の選定で注意すべき3つのポイント
法人携帯の経理処理では、以下の3点に特に注意が必要です。
- 科目の統一:同じ用途の費用は、すべて同じ勘定科目で処理すること。部署間や月ごとのバラつきは税務リスクになります。
- 私用利用の明確化:社員が私的に使う可能性がある場合は、福利厚生費とするか、給与課税との兼ね合いを確認しましょう。
- 証拠書類の保管:契約書・請求書・利用明細・MDM導入記録などは、科目選定の根拠になるため保管を徹底しましょう。
とくに最近では、インボイス制度や電子帳簿保存法の対応も進んでいるため、証憑類のデジタル管理も含めて社内でルール化しておくことが重要です。
会計ソフトとの連携|効率よく処理するには?
法人携帯の費用は毎月発生するため、会計ソフトとの連携によって経理作業の自動化・効率化が図れます。
以下は主要ソフトとの連携例です。
| ソフト名 | 連携できる内容 | 備考 |
|---|---|---|
| freee会計 | 法人クレカや口座連携で通信費を自動取得/ルール学習あり | 科目や摘要を自動で補完できる |
| マネーフォワードクラウド | 請求書データの自動仕訳・電子帳簿保存に対応 | リース・MDMもタグで管理可能 |
| 弥生会計 | 仕訳ルールを定義すれば再利用可 | 中小企業・個人事業主に根強い支持 |
なお、法人携帯の導入時には、会計ソフト側の設定変更(勘定科目の追加や摘要の整理)も忘れずに行いましょう。
【まとめ】勘定科目を正しく使って経費処理をスムーズに
法人携帯は、端末代・通信費・管理費用など、さまざまな費用が発生します。
これらを正しく処理するためには、「勘定科目の選定」が極めて重要です。
法人携帯の経費処理の主なポイント
- 法人携帯は通信費だけでなく、リース料・消耗品費・福利厚生費など複数の科目に分かれる
- 契約形態や使用目的によって、適切な処理方法が異なる
- 仕訳は会計ソフトと連携させることで、効率化・自動化が可能
経費処理の適正化は、税務調査のリスク軽減にもつながります。
ぜひ今回の内容を、社内での「ルール整備」や「帳簿管理」にも活かしてください。
👉法人携帯の経費処理でお困りの方は「法人携帯は経費で落とせる?処理方法・勘定科目・注意点を完全解説」をご覧ください。
帳簿管理については「法人携帯の管理台帳テンプレート付き|経費処理をスムーズにする運用術」を活用してください。
法人携帯に関する
お悩み・ご相談はお気軽に!
お客様の様々なニーズにお応えし、
ご利用に合う最適なプランをご提案します。